姿勢習慣病
shisei- TOP
- 姿勢習慣病
姿勢とは

姿勢という言葉は、その使われ方により多くの状態を意味します。姿勢とは、からだの構えです。伝統芸能や礼法などで、美しい姿勢と表現されますがこれは、静的姿勢から動的姿勢に変わるとき、無理なく移行できることを言っているようです。
また、正しい姿勢・いい姿勢といわれているのは、背すじの伸びた姿勢を指していますが、その代表的なものに、軍人が上官に敬礼したり、行進したりするときの姿勢、ファッションモデルがさっそうと歩く姿勢などがあります。
背すじは、それぞれその時の目的にあった形
茶道や日本古来の礼法でも背すじの伸びた姿勢が基本です。それでは背すじを丸くすることは悪いことなのでしょうか?
例えば、物事を考え込んでいるときなどは、背すじは自然と丸くなります。ロダンの彫刻の「考える人」はその典型です。また、相撲やボクシングでは、あごを引き背中を丸くした前かがみの姿勢でないと勝てません。
背すじは、それぞれその目的にあった形をとればいいと思いますが、トレーニング、エクササイズを目的とした場合には形態的な特徴をいかしながら、機能的な動き方をする事が日常生活動作には必要です。
姿勢習慣病について
ヒトの姿勢
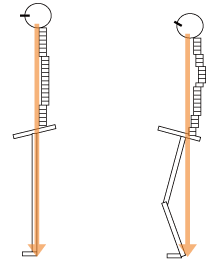
形態的特徴
- 立位直立
- 二足歩行
- 足の構造(アーチ)
- 踵が発達している
- 脚の端で直角に曲がった足
- まっすぐに伸びた膝
- 大きなお尻
- 横に広く前傾した骨盤
- S字の背骨
- 肩甲骨・胸郭の形
ヒトは小さな足に長い二本の脚を立て、脚の上に骨盤を乗せて、骨盤の上に内臓を入れる大きな体幹を乗せ、さらに背骨を骨盤の後から積み木のように積み上げ、体幹の上端に腕をぶら下げ、重たい頭を一番上に乗せてます。イメージは二本脚のテーブルに積み木(背骨)を積み上げ、天辺に重たいボール(頭)を不安定にのせた状態です。 このような不安定な状態なので、天板の傾き(骨盤傾斜)が変わることで、積み木の積み方やボールの位置が変化することは想像できます。また、それに伴い、ヒトのテーブルは脚が曲がったり、二本脚の幅が広がったりすることもあります。
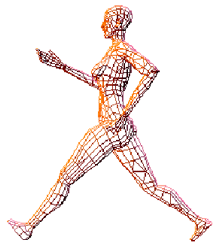
形態的特徴
- 頭部(重錘機能)
- 脊柱(身体支持機能)
- 骨盤(体幹支持機能)
- 上肢(手の機能)
- 股関節(骨盤支持機能)
- 膝関節(衝撃吸収機能)
- 足関節(支持安定機能)
- 足趾(支持安定機能)
ヒトが「動く」ためには身体の各部位それぞれの機能があって動作が完成します。正常に機能するためには正常な形態というのが前提となります。仮に怪我や障害などによって形態に変化しその部位が正常に機能しなくなると、他の部位が補いながら(代償)動作を繰り返すことになります。
姿勢変化

姿勢変化には、捻挫や骨折など外傷や障害により患部をかばい、歩行など動作を行いやすくするための比較的短期間で変化するもの(Short term change)と、身体的な変化(例えば加齢によるものと言われる症状)や動きのクセなど、長期期間に渡って繰り返し行うことによる変化(Long term change)があります。
姿勢変化の長短はありますが、その変化のパターンは大きくは4つに分類できると考えます。(?~?)
- 脊柱後弯→頭位前→骨盤後傾→膝屈曲→足関節底屈→下肢の支持機能の低下
- 骨盤後傾→膝屈曲→足関節底屈→下肢の支持機能の低下→体幹機能の低下→脊柱後弯
- 一側骨盤拳上→頭位偏倚→下肢伸展筋過緊張→膝関節・足関節可動域制限(同側内反/反対側外反)
- 足部扁平→下肢内旋→体幹屈曲→腰椎前弯→肩甲骨内転→肩関節伸展制限→骨盤後傾→脊柱後弯→体幹の回旋制限→下肢荷重軸の内側移動→膝関節内反
姿勢習慣病
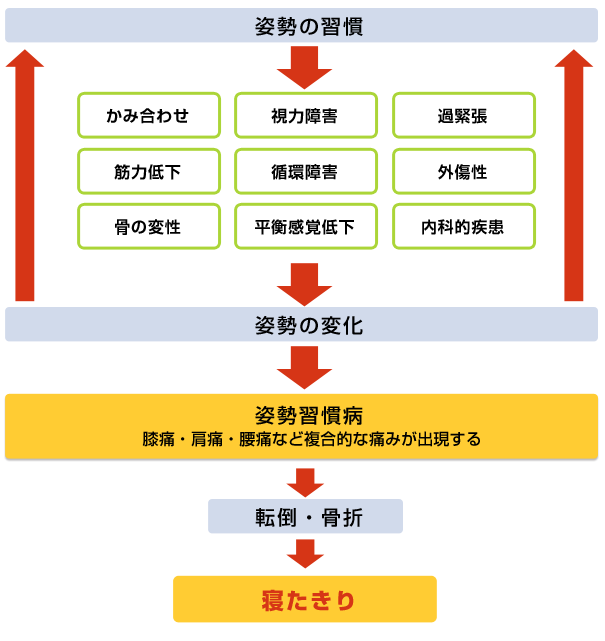
姿勢習慣病の定義
姿勢習慣病とは、姿勢習慣によって生じた身体の変化によって起こる状態、痛みの総称です。 頭部、体幹、上肢、下肢の相対的位置関係の変化(形態的変化)と、各部位がそれぞれ有する機能が果たせなくなること(機能的変化)により、他の部位に過度の負担が加わり、オーバーユースとなって痛みが発症する.痛みは動作初動時や複合的に日を変えて起こる。
姿勢習慣病には歴史があります
生活習慣病の名前はよくご存じだと思います。生活習慣病は糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満症、不眠症など内科系疾患の症候群です。「姿勢習慣病」は学会名ではなく整形疾患の症候群でもありません。姿勢が大切ですという呼称です。
<姿勢習慣病の由来>
故山嵜勉氏(理学療法士)は1997年昭和大学藤が丘リハビリテーション病院定年退職した。以降、著名な病院に非常勤で勤務、並びに当施設「ム・ウ21あざみ野」でもご指導いただいた。
著書として「形態構築アプローチの理論と技術 (理学療法士列伝―EBMの確立に向けて)をまとめられた。医療の切口と違う私たちの現場で運動療法の側面から姿勢習慣の歪みの積み重ねに着目し当施設では姿勢習慣病の呼称を考案した。
姿勢習慣が単に疾病の原因・発症・進行に関与する事とせず、機能的、形態的バランスの破綻による姿勢の変化と共に複合的な痛み等を発症する事を姿勢習慣病として2004年8月にまとめ、姿勢習慣病克服体操(転倒予防・寝たきり防止に効果的)を発表した。
以後ム・ウ21あざみ野の指導の柱となる。現在姿勢の重要性が見直され種々のエクササイズ・トレーニングがなされている。
